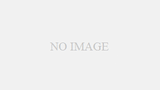高卒でフリーターやニートのまま将来に不安を感じている人にとって、資格取得は状況を変える大きな一歩になります。
中でも「宅建士(宅地建物取引士)」は、学歴に関係なく目指せる国家資格として注目されています。
今回の記事では、高卒フリーター・ニートが宅建士の取得を目指すのはありなのか詳細を解説します。
高卒フリーター・ニートが宅建士の取得を目指すのはあり
高卒フリーター・ニートが宅建士の取得を目指すのはありです。
宅建士は受検資格の制限がない
宅建士は「誰でも受けられる」国家資格です。
学歴や職歴に関係なく受験できるため、高卒フリーターやニートの方でも公平にチャンスがあるのが大きな魅力です。
例えば、大学を出ていない人でも合格すれば「宅地建物取引士」として不動産業界で堂々と働けます。
これは他の受検制限のない資格と同様に、「学歴に自信がない人でも資格で勝負できる」道を開いてくれます。
資格を取ることで、「高卒だから無理」といった思い込みを乗り越え、正社員就職のきっかけになります。
合格に必要な学習時間は300~500時間
宅建士試験の勉強時間は平均300〜500時間とされています。
フルタイムで働きながらでは難しいかもしれませんが、フリーターやニートなら時間を有効活用できる分、有利に働く可能性もあります。
独学でも合格している人は多数おり、書店で参考書を揃えるだけでスタート可能です。
近年ではYouTubeやアプリなど無料で学べる環境も整っており、学習のハードルも下がっています。
勉強に専念できる今こそ、宅建士に挑戦するチャンスです。
高卒フリーター・ニートが宅建士を取得するメリット
高卒フリーター・ニートが宅建士を取得するメリットを解説します。
就職で有利になることがある
宅建士の資格を持っていると、不動産業界などへの就職で有利に働くことがあります。
宅地建物取引業法第15条で、専任の宅地建物取引士の設置義務があるため、不動産会社では資格保有者は重宝されます。
また、学歴や職歴に不安がある人にとって、資格は「やる気」や「知識習得能力」の証明の1つにもなります。
そのため、何も書かないよりは履歴書に書いておく方が良いです。
高卒フリーター・ニートでも、業界への志望意欲を持っているとして企業へのアピールポイントになります。
年収アップ・キャリアアップにつながる
宅建士は資格手当がつくことが多く、正社員になった後も収入アップにつながります。
例えば、不動産会社によっては月1~2万円の資格手当が支給されるケースもあり、資格を持たない社員と比べて年間で数十万円の差が出ることもあります。
また、企業によっては宅建士が昇進や役職への登用条件になっている場合もあり、キャリアアップの面でも有利に働きます。
長く働きながら安定した収入を得たい人にとって、宅建士は心強いパートナーとなるでしょう。
不動産業界での活躍の幅が広がる
宅建士を取得すると、不動産業界での活躍の場が一気に広がります。
例えば、売買仲介や賃貸仲介以外に、独占業務である重要事項説明や重要事項説明書への記名、37条書面への記名も担当できるようになります。
また、不動産管理・不動産投資など、関連するジャンルの業務に携わる機会も増え、キャリアの幅が広がります。
「働きながら知識を増やし、さらに上を目指す」ことができるのも、宅建士資格の魅力です。
高卒フリーター・ニートが宅建士の取得を目指す際のデメリット
高卒フリーター・ニートが宅建士の取得を目指す際のデメリットを解説します。
合格率は低い
宅建士は人気資格の一つですが、決して簡単ではありません。
例年の合格率は15~17%前後とされ、しっかりとした学習が必要です。
特に民法や宅建業法の出題が多く、初学者には難しい内容も含まれるため、途中で挫折してしまう人も少なくありません。
独学で合格を目指すには継続的な努力と強い意志が求められます。
受験者の多くが社会人や大学生である中、学習計画の立て方やモチベーション維持の工夫が必要です。
その点、体系的に学べるLECの宅建士講座は、受講生の2024年度の合格率が75.2%と一般合格率の4倍もあるのでおすすめです。
宅建試験の5問免除は宅建業に従事している人が対象
宅建試験には「登録講習を修了すると5問免除になる制度」がありますが、これは宅建業に従事している人が対象です。
つまり、まだ不動産業界で働いた経験がないフリーター・ニートの方にはこの制度は適用されません。
勉強範囲が広い宅建試験では5問の免除は大きなアドバンテージとなるため、それを受けられないのは少し不利に感じられるかもしれません。
ただし、未経験でも合格している人は多数おり、あくまで「不利になる」だけで「不可能」ではないことも理解しておくべきです。
宅建士を活かせる仕事・職場
宅建士を活かせる仕事・職場を紹介します。
不動産営業
宅建士は不動産営業職で特に活かしやすい資格です。
不動産会社では物件売買や賃貸契約を行う事務所ごとに、専任の成年の宅建士の配置が義務付けられていて、資格を持っていることで評価されやすくなります。
重要事項説明など宅建士にしかできない独占業務があるためで、会社にとっても貴重な存在になります。
高卒フリーター・ニートでも資格を持っていると、正社員として採用される可能性があるためおすすめです。
ハウスメーカー・建設会社
ハウスメーカーや建設会社でも宅建士を活かせます。
不動産会社と同様に住宅の販売や土地の売買に関わるため、配置義務のある宅建士を持っている人は重宝されます。
例えば、申込契約を行うモデルルーム・モデルハウスは宅建士がいないといけません。
住宅営業職は未経験でも就職がしやすい職種で、高卒フリーター・ニートにもチャンスがあります。
銀行員
意外に思うかもしれませんが、銀行員は宅建士を持っている人が多くいます。
銀行では住宅ローンの審査や不動産担保の評価など、不動産に関わる業務が多く、宅建士の知識が大いに役立つからです。
例えば、融資の際に物件の法的リスクを見極めたり、顧客に対して正確な説明を行ったりする場面で宅建士の専門性が評価されます。
高卒フリーター・ニートが宅建士を取得して銀行員への就職は難しいですが、転職で目指すことは可能です。
宅建士取得後の就職活動の注意点
宅建士取得後の就職活動の注意点を解説します。
資格取得後の就職活動の進め方を確認しておく
宅建士を取っただけでは、すぐに就職できるとは限りません。
資格取得後は、どのような企業や職種に応募するかを明確にし、履歴書や職務経歴書に「自己PR
」「どんな仕事をしたいか」をしっかり記載しておきましょう。
正社員として働きたい場合は「未経験歓迎」や「宅建士資格取得者優遇」といった条件を探して、効率的に動きましょう。
その際、面接が苦手な人は就職エージェントやハローワークも活用すると効果的です。
資格以外の要素を見られる
宅建士を持っていても、面接では「人柄」「コミュニケーション能力」「やる気」など、資格以外の要素も重要視されます。
特に高卒フリーター・ニート歴がある場合、面接官は「この人が続けられるか」「職場に馴染めるか」を見ています。
自己PRでは、資格取得までの努力や計画性を具体的に語り、「働きたい意欲が強いこと」「仕事で貢献できること」を伝えましょう。
離職率が高い・ブラック企業が多い
残念ながら、不動産業界には離職率が高かったり、長時間労働、ノルマが厳しいブラック企業も存在します。
せっかく資格を取っても、入社してすぐに辞めてしまってはもったいないので、企業選びは慎重に行いましょう。
転職口コミサイトの企業レビューを参考にしながら、待遇や労働環境を確認し、できれば面接時にも働き方や離職率について質問すると安心です。
宅建士の取得理由を考えておく
就職活動では「なぜ宅建士を取ったのか?」という質問が必ず出てきます。
その時に「なんとなく」「就職できそうだったから」と答えてしまうとマイナス評価につながりかねません。
自分が宅建士を目指した動機や、不動産業界でどのように活躍したいかを整理しておくことが重要です。
例えば、「安定した仕事に就きたかった」「人の生活に関わる仕事がしたい」など、前向きな動機を用意しておきましょう。
まとめ
高卒でフリーターやニートの経験があっても、宅建士を取得することで就職やキャリアアップの可能性は大きく広がります。
国家資格である宅建士は学歴や職歴に関係なく受験することができ、努力次第で実務に活かせる専門性を身につけることが可能です。
不動産業界をはじめ、宅建士資格が活かせる職種は多く、正社員として働きたい高卒フリーター・ニートにとっては大きな武器になります。
ただし、資格を取るだけでなく、企業選びや選考対策など就職活動の戦略を考えておくことが必要です。
ブラック企業を避け、長く働ける環境を見極める力も求められます。
「資格を取ってから考える」のではなく、「資格をどう活かすか」を意識して行動することで、自分の将来を切り拓くことができるでしょう。
宅建士はその一歩を踏み出すための有力な選択肢の一つです。