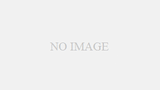高卒フリーターやニートの方が正社員を目指す際、「手に職がつく仕事」を選ぶことが成功のカギとなります。
その手に職がつく仕事の1つとして挙げられるのが、電気工事士です。
そこで、高卒フリーター・ニートが電気工事士を目指すのはありなのか詳細を解説します。
高卒フリーター・ニートが電気工事士を目指すのはあり
高卒フリーター・ニートが電気工事士を目指すのはありです。
学歴・経歴に関係なく挑戦できる
電気工事士は、学歴や経歴を問わず、誰でも挑戦できる職種です。
高卒フリーター・ニートであっても、第二種電気工事士の取得が可能であるため、「学歴が足りない」と諦める必要がありません。
実際、現場で活躍している電気工事士には、高卒や中卒からスタートした人も多く、資格があれば就職のチャンスが広がります。
第二種電気工事士の合格率は高い
電気工事士の入り口の資格である第二種電気工事士は、合格率が約60%前後と比較的高めです。
国家資格の中では難易度が低く、独学でも取得可能です。
実際に、資格取得支援を行うスクールや教材も豊富にあり、短期間で合格を目指せます。
合格しやすく、学習コストも低いため、第二種電気工事士に挑戦するのはおすすめです。
高卒未経験からでも正社員を目指しやすい
電気工事士の求人は、未経験者歓迎が多く、高卒フリーター・ニートからでも正社員を目指しやすい職種です。
電気設備業界は人手不足が深刻であり、資格さえ取得すれば就職先が見つかりやすいのがメリットです。
高卒や未経験でも「手に職をつけたい」「安定した収入を得たい」と考えている方にとって、電気工事士は非常に現実的な選択肢と言えるでしょう。
高卒フリーター・ニートが電気工事士になるメリット
高卒フリーター・ニートが電気工事士になるメリットを解説します。
国家資格で一生モノのスキルが身につく
国家資格である第二種電気工事士を取得すれば、生涯にわたって使えるスキルを身につけられます。
電気設備の工事やメンテナンスは生活や産業に欠かせず、資格があることで安定して仕事が得られやすいです。
現場での経験が増えるほど技術力が向上し、電気工事のプロフェッショナルとしての信頼が得られ、企業からの評価も上がります。
上位資格・関連資格の取得で年収アップを目指せる
第二種電気工事士の後は、上位資格や関連資格を取ることで年収アップを目指せます。
第一種電気工事士や電気主任技術者(電験三種)などを取得すれば、できる仕事が増えて、管理職や専門職としてキャリアアップできるからです。
また、施工管理技士や消防設備士などの関連資格を並行して取得すれば、電気工事以外の分野でも活躍が可能になります。
高齢化で安定した需要がある
電気工事業界では、電気工事士の高齢化が進んでいます。
地方や中小企業は深刻な人手不足に陥っていて、若い電気工事士が必要とされている状況です。
もともと景気に左右されにくい業界で、インフラ整備や設備更新の需要が続くため、長期的に需要が見込めます。
資格があることで「替えがきかない人材」として重宝され、業界の中で確固たる地位を築けるのが強みです。
AIに仕事を奪われにくい
近年、AIやロボットの導入で職業が失われるリスクが叫ばれていますが、電気工事士はその影響を受けにくいです。
現場ごとに異なる環境や作業条件があり、設備点検やトラブル対応は「人間の手と判断力」が欠かせません。
特に現場作業や電気配線の施工には熟練の技術が必要で、AIが完全に代替するにはまだ時間がかかるとされています。
将来的には独立開業も可能
第二種電気工事士の免状交付後3年以上の経験を積んで、勤務先から勤務記録証明書を発行してもらい、県に申請すると独立開業ができます。
独立することで自分のペースで仕事ができ、仕事量を自らコントロールできる点が魅力です。
勤務先でコネクションを作り、第一種電気工事士を取得しておくとより良いでしょう。
高卒フリーター・ニートが電気工事士になるデメリット
高卒フリーター・ニートが電気工事士になるデメリットを解説します。
休日に出勤しなければならない場合がある
電気工事士の仕事は、ビル・工場の電気設備メンテナンスや改修工事などが多いです。
稼働中の設備を止められないので、休日や夜間に作業が集中することが少なくありません。
商業施設や公共インフラの電気工事では、利用者が少ない時間帯に工事を行うケースが一般的です。
平日が休みになったり、不規則なシフト勤務になることもあるので、安定した土日休みを求めている人には、少し厳しいかもしれません。
しかし、企業によっては土日休みの場合もあるので、絶対ではありません。
体力が必要な場面がある
作業で使う工具は重く、高所や狭い天井裏で作業することもあるので、体力を必要とします。
工場やビルの設備管理では、一日中立ちっぱなしで仕事をすることもよくあります。
体力に自信がないと、長時間の作業や連続勤務に耐えられないかもしれません。
危険が伴う仕事である
電気工事は危険が伴う仕事です。
高圧電線や大型設備の工事では、感電や火災など重大な事故につながりかねないので、適切な保護具を着用して、安全意識を持って作業をしなければなりません。
高所での工事も多いので、転落しないように常に注意を払う必要があります。
就職後も継続的な学びが必要
電気工事士としてキャリアを築いていくうえで、就職後も新しい技術や法律改正に対応して学び続けなくてはなりません。
電気設備に関する法規や施工基準は定期的に見直されていて、最新の知識を持って業務に取り組まなければならないからです。
上位資格である第一種電気工事士や電験三種を目指す際も、同様の姿勢で知識を学ぶことが不可欠です。
第二種電気工事士の資格取得にかかる費用・時間
エントリー資格である第二種電気工事士の取得にかかる費用・時間を解説します。
受験料・工具代・講座費用など
第二種電気工事士の取得は、受験料や学習教材費、実技試験用の工具代を用意する必要があります。
- 受験料(ネット申込):9,300円
- 学科と実技の対策書籍:3,000~6,000円
- 工具セット(工具+練習):数万円
- 通信講座(利用する場合):2~7万円
- 免状申請費用:5,300円
トータルで5~10万円の範囲で費用が発生します。
独学の方が費用は抑えられますが、より確実に効率よく学ぶためには講座利用も検討しましょう。
目安の学習時間は100~200時間
第二種電気工事士の合格に必要な学習時間は、一般的には学科試験と実技試験それぞれでに50~100時間程度が目安です。
働きながら勉強する場合だと、1日1~2時間の勉強を3~6ヶ月間であれば無理なく続けられます。
早めに必要な教材や工具を揃え、計画的に学習を進めましょう。
働きながら資格を取ることも可能
第二種電気工事士は、働きながらでも取得しやすい難易度なので、現職の傍ら資格取得を目指す人も多くいます。
通信講座やオンライン学習を利用して、仕事の前後のスキマ時間を使って学べるので、効率的に勉強できます。
フリーター・ニートであれば、時間は十分に取りやすいので、その点は問題ないでしょう。
高卒フリーター・ニートから電気工事士になる方法
高卒フリーター・ニートから電気工事士になる方法を解説します。
第二種電気工事士を取得する
高卒フリーターやニートが電気工事士を目指す際は、最初に第二種電気工事士を取得しなければいけません。
試験は「学科試験」と「技能試験」の2つに分かれていて、学科試験では電気の基礎知識や法規が問われ、技能試験では実際の電気工事作業が評価されます。
独学は過去問を中心に問題形式に慣れておくとよいでしょう。
一方で、TACやヒューマンアカデミー![]() などの通信講座や資格学校を活用して効率的に学ぶのもありです。
などの通信講座や資格学校を活用して効率的に学ぶのもありです。
総合型の求人サイトで応募先を確保しておく
資格取得後の仕事探しは、総合型の求人サイトを中心に利用して応募先を確保しておきましょう。
資格名や勤務地、未経験歓迎を組み合わせて求人検索を行うと、応募できる企業が見つかります。
履歴書や職務経歴書の書き方は、求人サイト内のお役立ちコンテンツで事前に学んでおくとよいです。
面接では、「なぜ電気工事士を目指したのか」や「どのように資格取得に取り組んだか」を具体的に語ることで、採用担当者に熱意を伝えられます。
電気工事業界に特化したエージェント・求人サイトを利用する
効率的に就職活動をしたい場合は、電気工事業界に特化した就職エージェントや求人サイトを利用しましょう。
資格保有者を積極的に採用する企業が多く登録していて、未経験から正社員を目指せる案件も豊富です。
選考に自信がない人は、エージェントを利用するとキャリアアドバイザーが応募書類の添削や面接対策をサポートしてくれるのでおすすめです。
まとめ
電気工事士は、高卒フリーターやニートから正社員を目指すうえでおすすめの職種です。
入口の資格である第二種電気工事士は受験の制限がなく、合格率も高いので、独学も可能です。
需要が高いので、安定した収入やキャリアアップの機会を得られ、独立開業も目指せます。
挑戦する価値は十分にあるので、自分の可能性を信じて、一歩踏み出してみましょう。